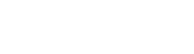シーベック効果とは何ですか?
シーベック効果は、回路内の2つの異なる金属間の温度差が電流に変換される熱電現象を表しています。ペルティエ効果は1834年に最初に観察され、トムソン効果は1851年に最初に説明されました。 1821年、Seebeckは、2つの異なる金属で作られた回路が、金属接続の2つの場所が異なる温度で保持されている場合、電気を伝導することを発見しました。シーベックは、彼が建てた回路の近くにコンパスを置き、針が偏向していることに気づきました。彼は、温度差が増加するにつれて、たわみの大きさが比例して増加することを発見しました。彼の実験はまた、金属導体に沿った温度分布がコンパスには影響しませんでした。ただし、彼が使用した金属の種類を変更すると、針が偏向した大きさが変わりました。
Seebeck係数は、導体の2つのポイント間に生成される電圧を記述する数であり、ポイント間に1度ケルビンの均一な温度差が存在します。 Seebeckの実験の金属は温度に反応しており、回路に電流ループと磁場が作成されていました。当時の電流に気付いていなかったため、Seebeckはこれが熱磁気効果であると誤って想定していました。
1834年、フランスの科学者であるジャン・チャールズ・アタナーゼ・ペルティエ(1784-1845)は、現在はペルティエ効果として知られている2番目の密接に関連する現象を説明しました。彼の実験では、ペルティエは金属導体間の電圧を変更し、いずれかの接合部の温度が比例して変化することを発見しました。 1839年、ドイツの科学者ハインリッヒ・レンツ(1804-1865)ペルティエの発見を拡張し、回路に沿った電流が流れる方向に応じて、接合部での熱伝達を説明しました。これらの2つの実験は、回路と熱電効果のさまざまな部分に焦点を合わせていましたが、それらは多くの場合、単にSeebeck-Peltier効果またはPeltier-seebeck効果と呼ばれます。
1851年、イギリスの物理学者ウィリアム・トムソン(1824-1907)は、後に最初の男爵ケルビンとして知られており、電流からの単一の種類の金属導体の加熱または冷却が電流からの加熱または冷却を観察しました。トムソン効果は、温度勾配にさらされた、電流を運ぶ金属またはその他の導電性材料で作成または吸収される熱速度を説明しています。
熱電対温度計は、シーベック効果とペルティエとトンプソンの効果の測定に基づいた電気工学ツールです。温度計は、熱電位差を電位差に変換することで機能します。