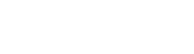供給の法則は何ですか?
供給の法則は、特定の製品の供給が増加するにつれて、その製品の価格も上昇することを示す基本的な経済原則です。これは通常、需要が高い新製品で見られますが、商品を含む他の多くの製品にも適用される場合があります。供給の法則と需要の法則はしばしば比較され、互いに使用されますが、独立した経済理論です。
供給の法則は、企業が価格が上昇するにつれて製品を生産することで利益を最大化する傾向があることを示唆していますが、それは常にそうではありません。確かに、企業が価格の上昇を見て、同じコストで製品を生産できる場合、できる限りその状況を利用できます。ただし、場合によっては、より多くの製品を生産すると、特定の非効率性が生じます。たとえば、企業は残業を支払うか、予定外の配達を求める必要がある場合がありますが、どちらも生産がより高価になります。これにより価格が上昇する可能性がありますが、利益率のみを維持するだけです以前のレベルで。
経済学では、供給の法則はしばしば供給曲線として知られているもので知られていますが、通常、モデルは左から右に上方に伸びる直線です。 X軸または水平線には量があります。 Y軸または垂直線には、価格のラインがあります。通常、モデルは一般的な参照のためだけに示されており、グラフで言及されている製品、価格、または供給量が記載されていません。
供給の法則と需要の法則との間には、2つの作業が手をつないでいるため、密接な関連があります。供給が価格とともに上昇すると、需要は最終的に低下します。最終的には、企業が過剰な在庫を取り除こうとするため、価格の下落につながります。多くの場合、2つの行は同じグラフに表示され、2つの別々の法律であるにもかかわらず、需要と供給の法則と共同で呼ばれます。一般的に、需要と供給は2つの反対fです需要と供給が平衡になるまで互いに反対するオルシス。
供給の法則は、利益を最大化することで企業がより多くの生産を奨励することを間接的に示唆していることを考えると、多くの人はこの法律を不況の期間中に経済を刺激する方法と見なしています。これらの個人は、サプライサイド理論として知られているものを購読しています。彼らはしばしば、民間部門を刺激し、経済成長を促進するために、企業に対する収入やその他の税金を引き下げる理由としてこの理論を引用しています。