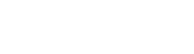比較優位の法則は何ですか?
比較優位の法則は、19世紀の最初の部分でイギリスのロンドンで働いているエコノミストであるデビッド・リカルドによって最初に提案されました。彼の作品は、アダム・スミスが提唱した絶対的な利点の理論など、以前の経済思想に基づいて構築されました。スミスは、絶対的な利点があった製品を使用して国が国際貿易に従事するべきだと示唆した。リカルドはさらに進んで、国が比較利点を持っている製品に特化することは理にかなっていると指摘しています。つまり、特定の商品やサービスを生産する機会コストは、他の国よりもその国で低くなっています。これらの商品やサービスを専門とし、国際貿易に従事することにより、国はその生産量を増やす可能性があります。
比較優位の法則は機会の概念を使用しています同じリソースの利用可能な代替用途を検討するコスト。たとえば、イングランドが20時間でチーズのユニットを、30時間でワインのユニットを生産できる場合、デンマークは10時間でチーズのユニットを生産し、25時間でワインのユニットを生産できる場合、デンマークは両方の製品で絶対的に有利になります。しかし、イングランドがワインのユニットを生産すると、1.5ユニットのチーズを生産するスキップがスキップしますが、デンマークは2.5ユニットのチーズをスキップし、デンマークが絶対に有利であるにもかかわらず、デンマークのワインをイングランドよりも大きく生産する機会費用をかけます。したがって、この例では、イングランドはワインを作る上で比較的利点があると言えます。イングランドがワインの生産を専門としている場合、デンマークがこの例で比較の利点を保持するチーズの生産を専門としている場合、両国は国際貿易に従事することで総生産量と国民所得を増やす可能性があります。
リカルドが提案するとおりの比較優位の法則生産コストは一定であるという仮定で、輸送コストはゼロであり、製品がどこであってもまったく同じであるということです。理論はまた、資本などの生産要因がモバイルであり、関税はなく、買い手と売り手が市場について完全な知識を持っていることを前提としています。この理論は、人件費のみを考慮しています。なぜなら、リカルドは、最後の分析のすべてのコストが人件費、つまり労働理論として知られるアイデアに削減される可能性があると判断したからです。現代世界では、比較優位の法則は、先進国と発展途上国の間の貿易に関連性があると見られるかもしれませんが、その運営は先進国間の貿易に関してはあまり明白ではありません。