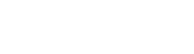頸動脈狭窄とは何ですか?
首にある頸動脈は、脳への酸素が豊富な血流の主要な供給源です。 頸動脈狭窄(CAS)は、これらの動脈が厚くてより狭くなると発生します。したがって、この必要な血液供給の一部を遮断します。 老化するにつれて、ほとんどの人で軽度の頸動脈狭窄が発生しますが、閉塞が大きくなるほど、影響を受ける人が脳卒中または一時的な虚血攻撃(ミニストローク)に苦しむ可能性が高くなります。 コレステロールと脂肪からのプラークは、動脈に蓄積する可能性があり、血流のための狭い経路を作り出します。 血液中の高レベルの血小板は、動脈内の凝固を形成し、経路を遮断することもできます。
脳卒中が動脈狭窄によって引き起こされると、通常、動脈が狭くなり、血栓が狭い点で蓄積して血栓を形成します。 血栓が血栓の後ろに蓄積すると、血栓は最終的に脳に渡される可能性があります。 さらに、血栓は防止します脳に到達することからの血液と流れの中断は、たとえ一時的であっても、脳細胞を殺し、脳機能を損なう可能性があります。
米国だけで毎年発生している60万ストロークのうち、約4分の1から半分が頸動脈狭窄によって引き起こされると推定されています。 したがって、早期の検出と治療は、米国で毎年150,000〜300,000ストロークを防ぐのに役立ちます。 CASの検出と治療は、症状と頸動脈が狭くなる程度に依存します。
場合によっては、毎年の健康診断中に、医師は聴診器を使用するときにブルーツと呼ばれる音を聞きます。 ブルーツが認められた場合、患者は頸動脈のドップラー超音波を受けて狭窄を確認する可能性があります。 頸動脈狭窄が検出されると、狭窄の程度を評価するためにさらなる検査が行われます。
血管造影またはカテーテル化は続きを使用します狭窄の輪郭を描き、測定するためにrast染料。 磁気共鳴画像(MRI)およびコンピューター断層撮影(CTスキャン)も使用できます。 ペースメーカーの患者の場合、MRIはペースメーカーの信号を中断できるため、禁忌です。血管造影には脳卒中のリスクがあります。 1つの非侵襲的検査であるOculoplethysmographyは、各眼の血圧を評価し、眼への有意な血流が頸動脈狭窄の影響を受けるかどうかを示すことができます。
残念ながら、頸動脈狭窄の最初の症状は、脳機能の障害、ミニストローク、または完全な脳卒中である可能性があります。 毎年の身体検査は、早期発見に役立つため、アドバイスされます。 CASまたは脳卒中のかなりの家族歴のある患者は、医師に通知する必要があります。 喫煙者と肥満はCASのリスクが高く、監視する必要があります。 コレステロール数が高い人も危険にさらされています。
CASが存在するが、動脈の50%未満をブロックしている場合、治療にはリスク因子の減少が含まれます禁煙、脂肪の低い食事、処方された運動など、さらなる狭窄。 これらは一般に、アスピリンなどの抗凝固剤を服用することと組み合わされます。 用量は非常に低く、本質的には1日あたり「赤ちゃん」アスピリン(81 mg)です。
ワルファリンのような他の抗凝固剤も処方される場合があります。 ワルファリンを伴う危険因子には、過度の出血と打撲を含めることができます。 ワルファリンを服用している人は、血液検査を介して綿密に監視され、特定の食事制限があります。
頸動脈狭窄が50%を超える場合、それを治療するためにいくつかの戦略が採用される場合があります。 頸動脈内膜摘出術は、外科医が動脈を開き、プラークの形成と閉塞を排除する外科的処置です。 合併症がないため、この手術を受けているほとんどは数日後に病院を出ます。 エンデルテクトル切除の影響は最大20年間続き、脳卒中の危険因子を大幅に減少させます。
場合によっては、全身麻酔のリスクが大きすぎる場合、CARdiologistsは頸動脈血管形成術を行います。 これには、一般的に太ももの動脈を通ってカテーテルを挿入し、頸動脈の狭い部分に通すことが含まれます。 そこに着くと、カテーテルに取り付けられたバルーンが膨らんで動脈を開きます。
バルーンインフレの後、ステントと呼ばれる中空の金属チューブが、動脈を開いたままにしておくために配置されます。 この方法の利点は、全身麻酔下では実行されないことです。患者は通常、処置中に意識があり、数時間後に家に帰ります。 ただし、これは比較的新しい手順であり、長期的な結果は利用できません。
頸動脈狭窄はそのような深刻な健康リスクを引き起こす可能性があるため、治癒するのではなく、防ぐ計画に従うことをお勧めします。 運動、賢明な食事、喫煙ではないことは、動脈の建物のプラークを減らすためのすべての方法です。毎年の検査は、初期段階で狭窄を捕まえるのにも役立つため、PROを避けるために行動のかなり単純な変化に焦点を当てることができます悲しみ。